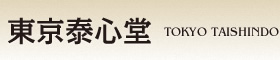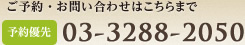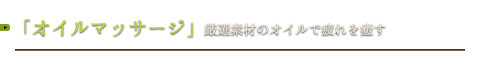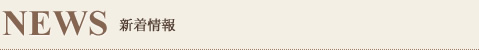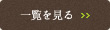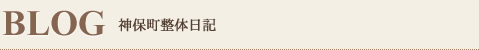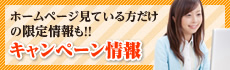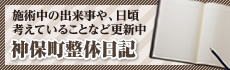-
2017.12.06年末年始のお知らせ
-
2017.12.01平成29年12月の予定
-
2017.11.01平成29年11月の予定
-
2013.09.09平成25年9月の予定
-
2013.07.207周年記念キャンペーン開催中
-
2013.02.22抗酸化物質を検証してみました。(Part5)
-
2013.01.18抗酸化物質を検証してみました。(Part4)
-
2012.12.25抗酸化物質を検証してみました。(part3)
-
2012.12.11抗酸化物質を検証してみました。(part2)
-
2012.12.02抗酸化物質を検証してみました。(Part1)